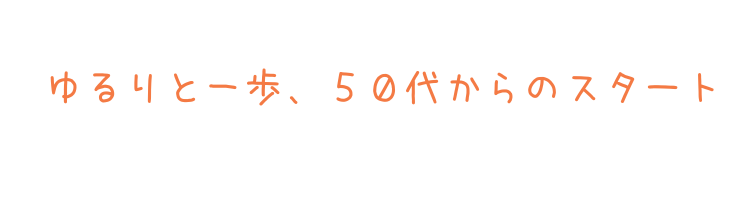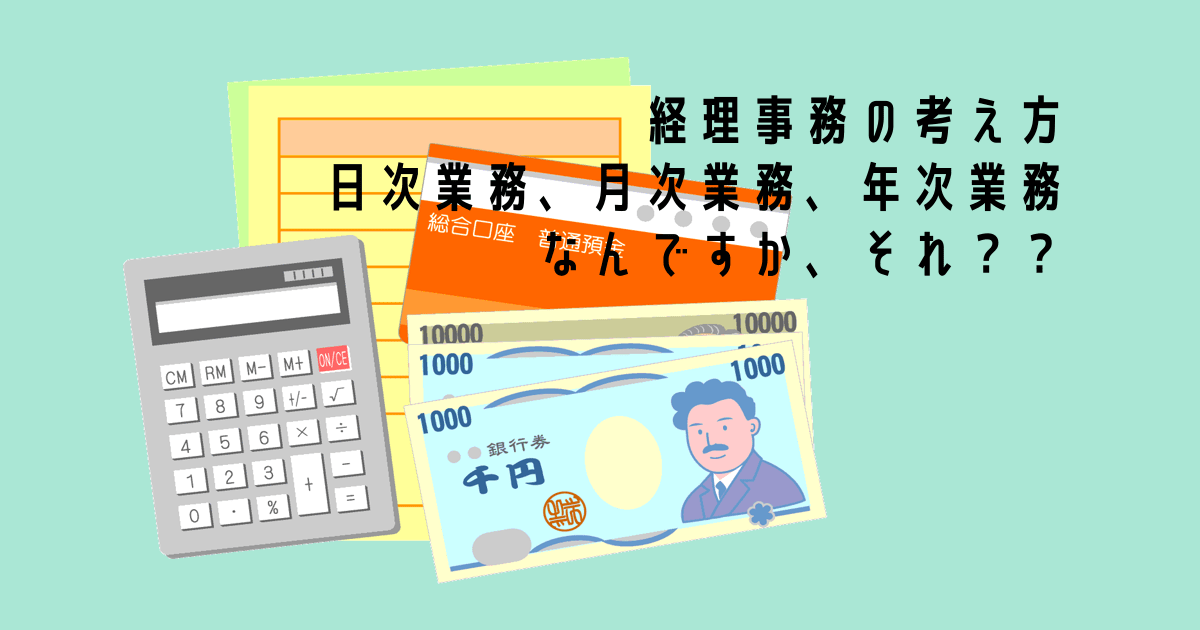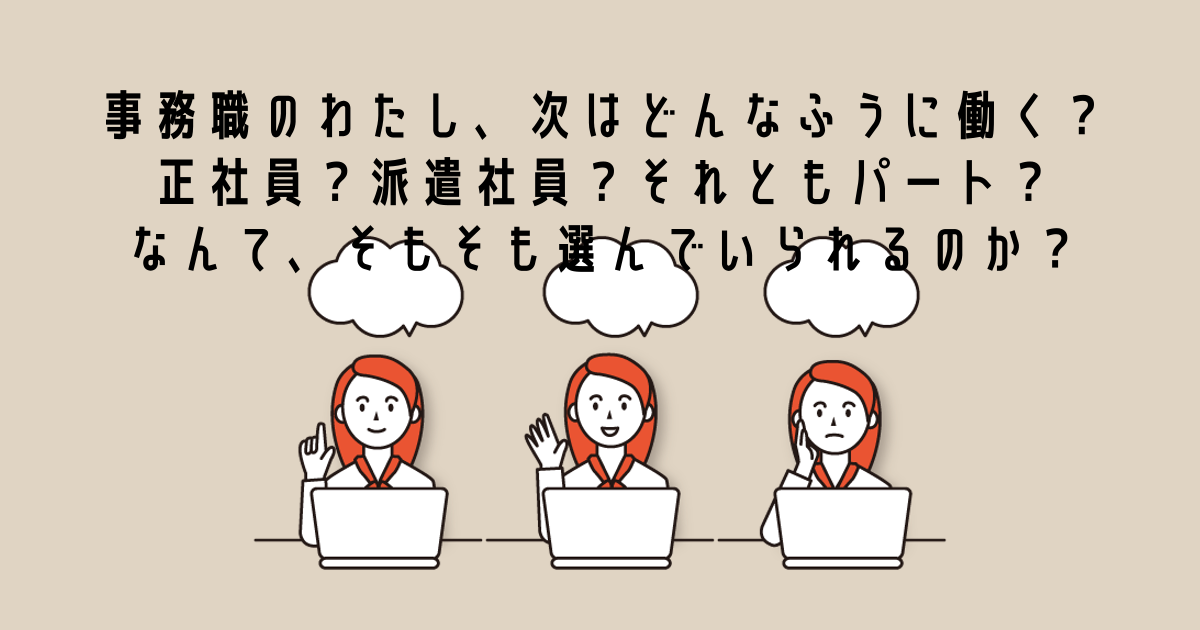私がはじめて経理事務の仕事に就いたのは47歳のとき。
以前にも経理部に所属したことはありましたが、そのときは一般事務。
しかも扶養の範囲内での仕事で、ファイリングばかりしていた気がします。
が、それも経理事務の経験といえば経験となりました。
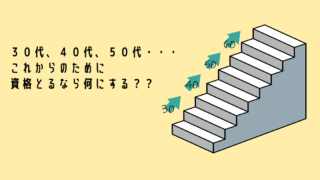
私は現在転職活動中ですが、企業の多くは3月決算であるため、経理事務の求人も年次業務がはじまるころに多いようで、今は・・・
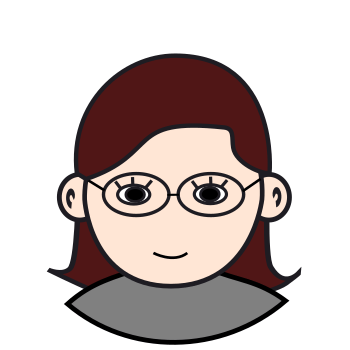
年次業務??はじめて聞きます。なんですか??それ。
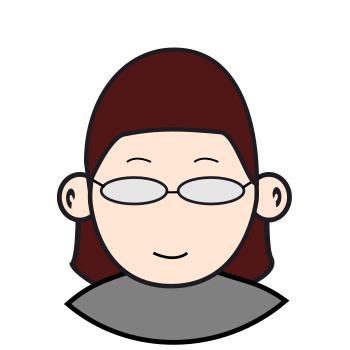
日次業務、月次業務、年次業務とは??
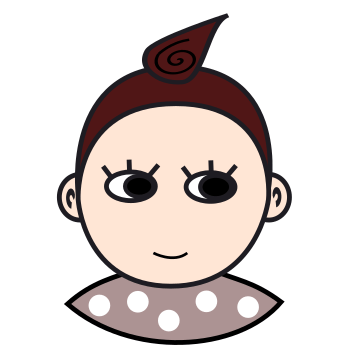
50代、すこしだけ肩のチカラが抜けてきたような。いまからでも遅くない。小さな一歩をちょっとずつ重ねていこう。ゆるりと焦ることなく、好きなことや好きなものを選んで自分らしく生きたい。そう思いながらも右往左往しているブログです。
将来、経理職に就くために簿記3・2級の合格を目指すなら【Accountant’s library】
![]()
経理の仕事-その1-日次業務
経理の仕事は毎日行う日次業務、毎月行う月次業務、年度末に行う年次業務があります。
その中の日次業務とは、ざっくりいうと日々発生するお金の動きの管理です。
一般家庭でもお財布に現金が出たり入ったりするように、会社でも現金の出入りがあります。
これを毎日記録し、帳簿上と実際の金額が一致しているかを確認します。
また、一般家庭でも銀行の通帳が紙やWEB上であると思います。
お財布の現金を出し入れしなくても通帳には、給与が入っていたり、ちょっと利息が入っていたり、携帯代が引落されたりします。
会社も同様に、現金以外の預金があります。
取引先とのやりとりや水道光熱費や従業員の給与や経費など、現金ではなく普通預金や当座預金を使ってお金が動きます。
こうした預金の入出金管理も日次業務のひとつです。
今はネットバンキングと会計ソフトを連動させることもありますが、その場合も、人間がひとつひとつ内容を確認します。
一般家庭と違うのは、会社の場合は、現金や預金のお金の動きには必ず、伝票や、それに付随する根拠資料が必要となる点です。
こうしたものを起票、作成するのも経理事務の日次業務となります。
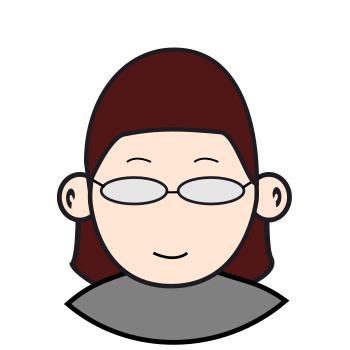
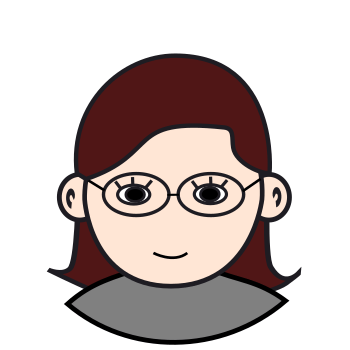
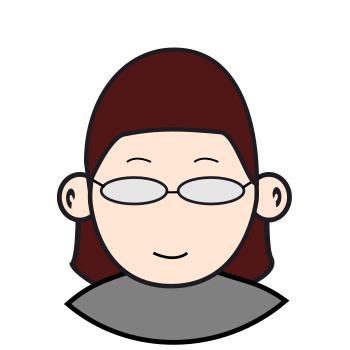
これらの日次業務を正しく行うことで次の、月次決算、年次決算がスムーズにすすめられるようになるのよ。
経理事務ってかなり地道でコツコツした「積み重ね業務」だと思うわ。
経理の仕事-その2-月次業務
月次業務は月単位での会社の状態を知るためのものです。
月次業務は会社の規模や業種などによって異なる部分も多くありますが、ここで理解が必要になるのが計上月の「月の感覚」です。
この支払は何月分の仕入か、この入金は何月分の売上か。
この計上月の「月の感覚」が間違っていると正しく業務をすすめられません。
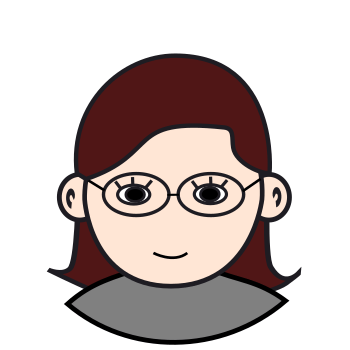
例えば今日が8月1日だったとします。
すると、今日やる月次は7月の月次です。
7月31日までの売上や支払や給与や経費や水道光熱費などなど、7月が終わらないとわからないため、8月に入ってから7月月次をスタートします。
もしも、7月31日の10時に7月月次をはじめてしまい、7月31日の15時になって売上が発生したら、その売上を7月分として含めることができなくなってしまいます。
そうなると、7月時点での会社の状態を正しく把握することができなくなります。
このとき、対象の売上の入金が8月31日の予定でも9月30日の予定でも関係ありません。
7月の売上かどうかが大切になります。
以上の理由から、通常は7月が終わった8月1日以降の決まった期間内に「7月月次」を行います。
経理事務の派遣社員の求人には、「月末月初のみの仕事です」というものがあります。
これは月末月初が経理にとっての「繁忙期」だからです。
月末は支払業務や入金確認、月初は前月分の月次業務、これらを簿記のルールに則ってすみやかに行えるよう、人材が必要だからです。
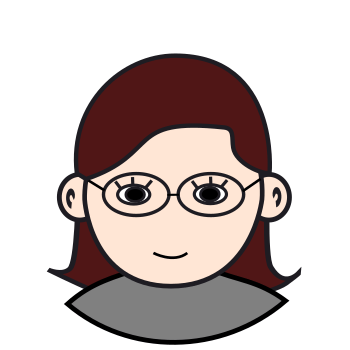
経理の仕事-その3-年次業務
年次決算は会社にとって1年に1度の総まとめです。
月次決算と同様に、1年が終わった翌日から作業に入ります。
年度の中で未処理はなかったか、年に一度の処理を確認するなどし、簿記のルールに則って修正をします。
こうして会社として決算書を作成し、消費税や税金を計算し、数字が決まったら、申告、納税を行います。
通常の月次業務もあるため、経理にとっては最も多忙な時期です。
年次決算をスムーズにするためにも月次決算をしっかりと終えておくこと。
そのためには日々の日次業務を正確に行っておくことが重要です。
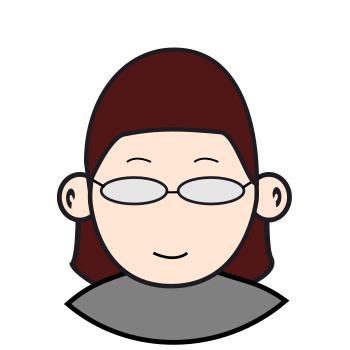
まとめ
経理では、ふつう家計簿では見かけない売掛金、買掛金、未払金、未払費用、前払費用などといった、「勘定科目」があります。
この科目を月次業務や年次業務で「振替え」たり「振戻し」たり、また、費用や収益の勘定科目を使って「見越し」たり「繰延べ」たりしながら会社の現状を正確に把握できるようにします。
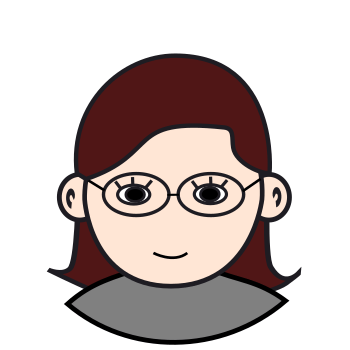
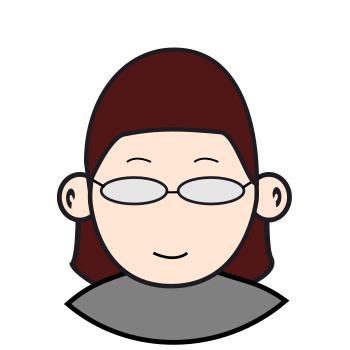
これらを理解するには、日商簿記の資格を取ることが近道よ。
以上、日次業務、月次業務、年次業務のお話でした。